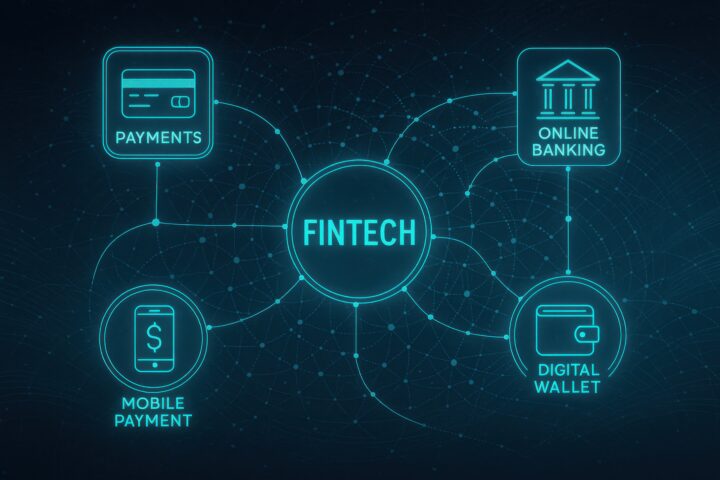フィンテックが誕生して10年、日本のフィンテックは大きな転換点を迎えています。2025年フィンテックを展望するシリーズ記事の最終回となる今回は、2025年の10の注目トレンドについて、その重要性と関連する企業事例を交えながら解説します。
目次
マス市場獲得に向けたパートナー連携が活発化
日本のフィンテックが、いよいよアーリーアダプター層を超えてマス層の一般ユーザーに広がっていきます。サービスの革新性だけでなく、既存の顧客基盤へのクロスセル、そのためのブランド力、そしてコンプライアンス体制などの要素が不可欠です。フィンテック企業と歴史ある金融機関が手を組み、互いに補完しあいながらマス市場を獲得していくトレンドが鮮明になります。
最近の事例から幾つかの例を挙げます:
- 三菱UFJファイナンシャル・グループがロボアド最大手のウェルスナビを子会社化(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241129/k10014653421000.html)
- マネーフォワードが家計簿アプリを分離、三井住友カードから出資を受ける(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001276.000008962.html)
- 住信SBIネット銀行アプリからデジタル証券のオルタナに誘導(https://www.netbk.co.jp/contents/company/press/2024/1120_003073.html)
- みずほ銀行とGMOインターネットグループで企業間決済システム(https://www.mizuhobank.co.jp/release/pdf/20241206release_jp.pdf)
- 三井住友ファイナンシャル・グループとインフキュリオンで法人向け決済サービス(https://www.smbc.co.jp/news/pdf/j20240927_01.pdf、https://infcurion.com/news/news-20250415_001/)
参考:インフキュリオン・インサイト、「2025年は「フィンテックが日常に溶け込む年」」、2025年2月5日
競争力の源泉はモダンな金融ITインフラ
ユーザーにシームレスな体験を提供するためには、企業間の境界をまたいだ即時性の高いシステム連携が求められます。API(Application Programming Interface)などを活用し、リアルタイムでのデータ連携や機能の共有を可能にするモダンな金融ITインフラが、フィンテック企業の競争力を大きく左右します。
事例としては、JR東日本の「JRE BANK」に楽天銀行が金融機能を提供、Kyashの「Kyash スポットマネー」にアコムの100%子会社であるGeNiEが金融機能を提供、Finswerの「Finswer Bank」に北國銀行が金融機能を提供する、などがあります。Embedded Finance型のサービスが、モダンな金融ITインフラによって実現されています。
参考:インフキュリオン・インサイト、「キャッシュレスとAPIが導く2025年のEmbedded Finance新時代」、2025年3月4日
複線化するユーザー獲得戦略
個人と法人の間に存在する関係性(例えば雇用関係)を活用し、BtoBtoC(Business to Business to Consumer)、BtoCtoB(Business to Consumer to Business)といった複線的なアプローチで顧客を獲得することが、新たな成長戦略として重要になっています。
デジタル給与サービスは、企業(B)が従業員(C)に給与を支払う際に、従業員が指定する資金移動業者の口座で受け取れるようにするもので、PayPayやリクルートMUFGビジネスなどがサービスを提供しています。これは、法人(B)経由で従業員である個人(C)を獲得するBtoBtoCの事例と言えます。
中小企業のデジタル化最前線は「支払DX」
中小事業者(Small- and Medium-sized Enterprise; SME)のデジタル化において、受発注、決済、経理などのバックオフィス業務の効率化は重要な課題です。特に、請求書の電子化や支払業務のデジタル化(支払DX)は、生産性向上に大きく貢献します。使い勝手の良いソリューションが不足していたSME市場ですが、バックオフィス向けビジネスサービスに決済機能を組みこんだEmbedded Finance型ソリューションによる「支払DX」が拡大しています。
経理業務、請求書業務でのクラウド型サービスやSaaS利用が浸透しており、特に「請求書カード払い」や「従業員向け経費精算プリペイドカード」が支払DXを強く後押ししています。
参考:インフキュリオン・インサイト、「データで見る法人向けEmbedded Financeと「支払DX」の必然」、2025年4月28日
混戦化するキャッシュレス決済 単価による棲み分けの崩壊
キャッシュレス決済市場では、クレジットカードとコード決済の競争が激化しています。これまでは「高単価なクレジットカード」と「高頻度なコード決済」という暗黙の棲み分けがありましたが、2025年にはそうした棲み分けは崩壊し、利用獲得を巡る競争が激化します。
タッチ決済の急速な普及が、クレジットカードによる少額決済を拡大させています。自販機や交通機関でのタッチ決済の広がりに注目です。コード決済も、アパレルやガソリンスタンド、百貨店など高額帯での利用が増えており、クレジットカードの牙城に進出してきています。
送金型サービスの多様化と利用拡大
従来の銀行振込に加え、コード決済アプリや、ことら送金、デジタル通貨、ステーブルコインなど、多様な送金サービスが登場しており、個人に多様な選択肢を提供しています。特に、コード決済アプリでの送金利用の拡大は顕著です。また、企業間決済をターゲットとしたサービスも続々投入されてきています。。
コード決済アプリは数千円程度を手軽に送る手段として定着してきています。銀行振込も利便性向上が見込めます。2025年11月には銀行振込を支える全銀システムにおいて「APIゲートウェイ」が稼働予定であり、資金移動業者として初めてワイズ・ペイメンツ・ジャパンが接続予定となっています。預金を裏付けとするデジタル通貨や、法定通貨と連動したステーブルコインの中には、企業間決済向けと位置付けられたものも現れています。
生活・業務への溶け込み 与信サービスのレベルアップ
2019年に開始された「LINEポケットマネー」は「ちょっとした資金需要」に対応したサービスとして、ユーザーの生活に溶け込んだ与信サービスの好例です。Embedded Financeはこのように、与信サービスの生活・業務への溶け込みを促進します。最近の成功事例としてはGeNiEの「マネーのランプ」を活用したKyashの「Kyashスポットマネー」が挙げられます。
クレジットカードの「利用限度額」や「返済タイミング」を柔軟化することで新たなユーザー層の開拓に成功している例としてはナッジ株式会社の「ナッジカード」があります。
SME向けでも、ファクタリングやAI融資など、使い勝手を大きく改善した与信サービスが登場し着実に利用を増やしています。
2025年4月からはCIC「クレジット・ガイダンス」の企業向けの提供が始まっています。与信モデル改善や、新規参入の障壁を低減可能性に注目です。
急成長するデジタル証券市場
ブロックチェーン等の技術を活用して発行・管理されるセキュリティトークン(ST)は、新たな資金調達手段や投資対象として注目されており、市場が拡大しています。
株式会社Progmatによると、ST案件の新規組成額は増加傾向にあります。
本格化する生成AIの業務活用
金融業界でも、生成AIを活用して業務効率化や顧客体験向上を図る動きが活発化しています。特に、定型業務の自動化や、顧客対応の高度化などが期待されています。
面白い先進事例としては、米国のSME向け会計SaaSであるIntuitのAIエージェント「Intuit Assist」があります。請求書の自動生成やキャッシュフロー予測など、業務プロセスに溶け込むAIのイメージとして大いに参考になります。
活用広がる公的個人認証
総務省によると、2025年4月末時点でのマイナンバーカードの保有率は78.5%。マイナンバーカードによる公的個人認証は、オンラインでの本人確認手段として、安全性と効率性を両立できるため、金融サービスにおける利用が拡大しています。例えば口座開設における公的個人認証は、住信SBIネット銀行やメガバンクなどが既に対応しています。
警察庁は銀行やクレジットカード会社などが行う非対面の本人確認を、マイナンバーカードによる公的個人認証に原則一本化する方針を示しました。犯罪収益移転防止法施行規則を改正し、2027年4月1日の施行を見込んでいます。しかし、新たな制度の施行を待たずに、多くの金融事業者やフィンテック事業者が公的個人認証への対応を自ら推進してゆくことになるでしょう。
出典:
- 総務省、「マイナンバーの保有状況について(令和7年4月末時点)」(https://www.soumu.go.jp/main_content/001008013.pdf)
- 警察庁、「「国民を詐欺から守るための総合対策」の決定について(通達)」、2024年6月18日(https://www.npa.go.jp/laws/noaction/sogotaisaku.pdf)